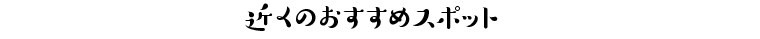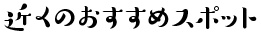明治10年(1877年)の2月から9月にかけて激戦が繰り広げらた西南戦争。戦火は九州の広範囲へと広がり、現在の曽於市も戦場となった。
西郷隆盛を盟主とする薩軍は熊本方面に兵を出すが、熊本城攻めの失敗や田原坂の敗戦から劣勢となる。官軍の攻勢に人吉から横川、霧島山麓へと押されていく。鹿児島も官軍が制圧し、大隅でも国分・垂水・鹿屋・志布志・大崎などを官軍が押さえる。薩軍は都城・宮崎方面へと追い込まれていくことになる。
曽於が戦場となったのは7月頃。薩軍としては、巻き返すためにもなんとか踏ん張りたい、という状況であった。村田新八が指揮をとり、都城を拠点に官軍を迎え撃つことになる。財部・末吉・岩川は都城の手前の防衛戦線であった。
鹿屋・志布志・大崎方面より侵攻する官軍に対して、薩軍は恒吉や岩川に兵を置き、ここから市成・百引(ともに現在は鹿屋市輝北町)などへ討って出る。局地戦での勝利はあったものの結局は劣勢となり、薩軍は末吉に退却した。恒吉や岩川も官軍に奪われる。
霧島山麓方面では、大口・横川を落とした官軍が東へ。これを薩軍が迎え撃ち、大川原や十文字原など財部一帯に戦火が広がった。福山方面から進軍する官軍に対しては、通山に陣取って交戦。佳例川周辺(霧島市福山町佳例川と曽於市財部町南俣・大隅町坂元のあたり)で激戦が繰り広げられた。
薩軍は末吉と通山に陣を置き、しばらくは官軍と対峙。しかし、7月24日に官軍は総攻撃を仕掛ける。財部の十文字原や日光神社並木道の戦いで官軍が勝利し、通山と末吉も陥落。官軍は都城へ突入した。薩軍は建て直すことができず、都城を放棄して宮崎方面へ退却した。
その後、宮崎・延岡の戦いで薩軍は敗北し、8月16日に軍を解散。西郷隆盛と軍に残ったものたちは官軍の包囲網を突破して、9月に鹿児島に戻る。城山にたてこもるが、9月24日の総攻撃をもって西南戦争は終結した。